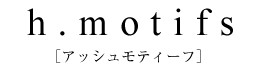12月の料理教室
2023/12/27
12月はクリスマスメニューです。
乾杯はエルダーフラワーコーディアルを炭酸水で割ったノンアルカクテル。 レモンとローゼルの花びらと共に。
烏賊と洋梨のサワークリーム和え
今月の冷たい前菜。 不思議な組み合わせだけど今一番の推し!
材料を切って混ぜるだけ。白+緑の素材(烏賊、セロ、ディル、ディル)の一皿は聖夜にピッタリ。
ビーツのチーズディップ
人が集まる場ではこんな一品があると重宝します。 スウィーツと見間違えそうな鮮やかな色はビーツのおかげ。 見た目とは裏腹な根菜らしい力強さとクリームチーズが相性良し。
クリスマスらしく胡桃、ピンクペッパー、タイムをトッピング。
そのままでも、バゲットにのせても。
蟹とごはんのスフレ
温かい前菜。ベースはホワイト(ベシャメル)ソース。 具材は蟹と炊いたごはんとチーズ。 香るハーブはエストラゴン(英名タラゴン)。
オーブンで焼く直前にメレンゲを加えて、ホワホワの生地を型に流して焼く。
手順はシンプル。 なによりタイミングが重要。
生地が高く盛り上がり、焼き色がついたら食卓へ運ぶ。
「スフレ」はフランス語で「膨らんだ」という意味の言葉。
焼きたてをすぐ食べる。それがこの料理を一番楽しむ方法です。
カリフラワーと柿とベビーリーフのサラダ
シンプルな玉葱ドレッシングで和えたサラダ。カリフラワーの食感と柿の甘みがポイント。
牛肉のビール煮込み(Carbonadeカルボナード )
この夏訪ねたベルギーへのオマージュ?を込めてベルギービールを煮込みに使いました。
いわゆる「取りあえずビールで・・」の一杯ではなく、コクも香りも異なるビールです。
一番大変だったのはどのビールを採用するか?
ま、これを口実に夏から何度も試飲&試食を重ねてきたのですけど。
ベルギービールの特徴として瓶内で二次発酵させるものが多いこともあり、輸送コスト、円安状況など、輸入食材を使う意味についても考える機会を得たようにも思います。
結局、比較的入手しやすく、いくつかバリエーションがあり、これをきっかけに「新たなビールの世界」を広げていけそうな(勝手な思い込みですが)名前も覚えやすいシメイ(CHIMAY)レッドを採用。 ビールの画像正面の赤いボトルです。
価格もアルコール度数も高めですが、いつもと違うクリスマスとなればなにより。
食材は牛すね肉と玉葱。 調味料は白ワインヴィネガー、デイジョンマスタード、赤砂糖(甜菜糖で代用)、塩、胡椒。
煮込み時間はかかりますが、手順は簡単。
北フランスからフランドル地方の郷土料理ですが、ブルゴーニュの名産品のデイジョンマスタード、ヴェルジョワーズと呼ばれる赤砂糖、白ワインヴィネガーなどフランス料理らしい調味料を使うことなど、なかなか意味深い料理です。
付け合わせにはフレンチフライ(フライドポテト)が一般的ですが、日本人の胃袋に合わせマッシュポテトを添えました。 ホロリと煮込まれた牛肉の甘さと数秒遅れでやってくる苦みとを楽しんでいただけたら嬉しいです。
ガトー・ベル・エレーヌ(Gateau de Belle Helene)
現代フランス料理の父エスコフィエが考案したと言われるベル・エレーヌ。洋梨のコンポートにチョコレートをかけたデザートです。
洋梨を入れたバターケーキにチョコレートをたっぷりとかけたらクリスマスに相応しいお菓子がつくれるのでは?と発案。
洋梨のやわらかさに合わせてケーキ生地もきめの細かいやわらかさを目指しました。
ケーキを焼き上げて、チョコレートを流し、固まったらすぐにも食べられますが、2日後くらいがベストな食べ頃。 ケーキ生地と洋梨とチョコレートが良く調和していると感じます。
クリスマスにかける参加者皆様の熱気に圧倒されつつ、今年も教室へご参加いただき、ありがとうございました。
来年も皆様のパッションを栄養源とし(笑)教室を開いていきます。 よろしくお願いいたします。